
リフォーム営業の求人が気になっているけど、リフォーム営業の仕事内容って具体的にどんなものがあるの?

リフォーム営業の仕事は、リフォーム工事の提案やお客様との打ち合わせ、現場の管理などたくさんあります。
この記事では、元リフォーム営業の筆者がリフォーム営業の良いところも悪いところも徹底的にお教えします。
古くなった家は建て替える、というのが一般的だった日本ですが
近年は住宅リフォームが浸透してきて、リフォーム工事のニーズが大きく伸びています。
リフォーム工事のニーズが増えたことで、リフォーム営業の求人も増えてきました。
これからリフォーム関係の求人はますます増えていくと思います。
この記事では、元リフォーム営業の筆者が、リフォーム営業の仕事について1〜10まで解説します。
リフォーム営業の仕事が気になっている方は、参考にしてみてくださいね。
・リフォーム営業の仕事内容
・リフォームの仕事に就くことへの不安
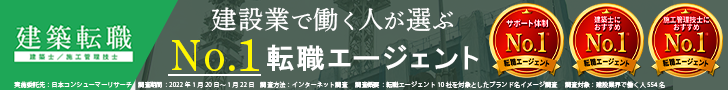
・リフォーム営業の仕事内容
・給料や勤務時間などの待遇面
・リフォーム営業の将来性
・リフォーム営業になる方法
すこし長い記事なので、気になることが決まっている方は目次をご活用ください。
それではいってみましょう!
元リフォーム営業が教える!リフォーム営業の仕事
リフォーム営業の仕事は、他の営業職とは少しイメージが異なるかもしれません。
理由は営業活動以外に、現場サイドの仕事も多いからです。
順を追って解説します。
仕事の流れ
- 新規のお客様から会社窓口に連絡
↓ - お客様へご連絡、アポイントをとる ←実質ここからスタート
↓ - 現地調査、お打ち合わせ
↓ - 見積もり作成
↓ - 商談、ご契約
↓ - 工事日程の段取り
↓ - 工事申請や発注業務
↓ - 現場監理
↓ - 工事完了後、物件のお引き渡し
大まかな仕事の流れはこんな感じです。
反響営業と飛び込み営業
リフォーム営業には、おおまかに「反響営業」と「飛び込み営業」の2パターンがあります。

はじめまして!茂吉工務店のもきちと申します。近くでリフォーム工事店を営んでいるんですが、お家のお困りごとはありませんか?
いうまでもないですが、知らない家に訪問していくのが「飛び込み営業」ですね。
逆に「反響営業」は、フリーダイヤルなどの総合窓口を設けて、家のお困りごとのあるお客様から連絡をいただくパターンです。
実際に経験のある方に話をきいたところ、飛び込み営業は相当きつくてメンタルがやられるそうです。
もし勤めるなら、圧倒的に反響営業の会社がおすすめです。
一気通貫型と分業型
リフォーム営業には2つのスタイルがあります。
詳細は会社によって違いますが、よくあるのはこんな感じ。
一気通貫型
アポどりから商談、現場監理まで1人で全て行う。
前項「仕事の流れ」 2〜9まで
分業型
お客様対応のみを行う。
見積もり業務や、現場監理は別の担当に任せることができる。
請負金額が500万以上など、大きな案件専門でやっている会社で多いスタイル。
前項「仕事の流れ」 2、3、5、9
仕事のやりがい
- 1から自分で手がけられる仕事
- 個人の裁量が大きい
- お客様に感謝される
- 自分次第で大きく稼げる
⒈1から自分で手がけられる仕事
1から10まで自分で手がける仕事って意外と少ないと思うんです。
リフォーム営業をする上で、お客様の悩みを解決するプランを立案するのは自分。
そしてそのプランを実行するのも自分です。
大変なこともありますが、苦労して作り上げたものが自分のイメージ通りに出来上がったら…
できあがったものを見たときの感動はひとしおです。
⒉個人の裁量が大きい

もきちくん、この書類まとめて、終わったらこっちの書類もお願いね!

わかりました。終わったら報告します。
上司から頼まれた仕事をたんたんとこなす、という場面はほとんどありません。
担当する案件に対して、どうやったら契約してもらえるかを自分で考えて動きます。
そのため、仕事のやり方も、スケジュールも自分の裁量次第です。
筆者は仕事中に、サロンの予約を入れて髪を切りに行くこともありました。
(↑会社によっては怒られるので鵜呑みにしないでくださいね)
⒊お客様に感謝される
どんな仕事でも自分で考え、動いた結果、人に感謝されるというのは気持ちのいいものです。
お客様から直接感謝の言葉をもらえる仕事って、案外多くありません。
リフォーム営業は自分の提案次第で、お客様から本当に感謝されます。
お客様に感謝してもらえると、仕事を頑張る活力になりますよ。
⒋自分次第で大きく稼げる
正直筆者は、これが一番大きなやりがいになりました。
あとで年収の話はしますが、経験や年齢を問わず、自分の売り上げ次第で収入が変わります。
年収1000万以上稼いでいる人の話も聞きます。
お金が全てとは言いませんが、収入が増えれば生活が豊かになりますし、人生の選択肢も増えます。
どのくらい稼げるかはやりがいに大きく関わってきますよね。
リフォーム業界はクレームが多い
リフォーム業界に入る前に知っておいて欲しいのですが、リフォーム業界はクレームが多いです。
そもそも建築業界は「クレーム産業」と言われるほどです。
クレームが多い主な原因としては以下のことが挙げられます。
⒈ 仕上がりがイメージしづらい
⒉ リフォーム営業の知識不足
⒊ 工事の音がうるさい
⒈仕上がりがイメージしづらい
リフォーム工事は、そこにある商品を買って終わり!というものではなく、工事が終わるまで実物が見れません。
プロである工事店側ならともかく、素人であるお客様からしたら完成イメージがつきづらいものです。
そこでイメージの共有がうまくできていないと、クレームに発展するケースがあります。
⒉ リフォーム営業の知識不足
リフォームではさまざまな知識が求められます。
知識がないばかりに間違った施工方法を取ってしまうとクレームに発展します。
この手のクレームは、経験、知識が増えるにつれ、少なくなってきます。
わからないことは事前に調べておくことで、未然に防ぐことができます。
⒊⒊ 工事の音がうるさい
リフォーム工事は大きな音が出ることが多いです。
そのため、近隣から騒音のクレームが寄せられることもあります。
工事前には、近隣への事前説明やご挨拶をしておくことが大事です。
高収入が目指せる!リフォーム営業の待遇面について
ここからは、リフォーム営業の給料や休日などの待遇面のお話をしていこうと思います。
会社によって異なるので、1つの目安として参考にしてみてください。
給料、平均年収
リフォーム営業の給料体系は成果報酬制が多いです。
自分の売り上げた金額の〜%がインセンティブとしてもらえる、というシステムですね。
給料は自分の成績次第ですが、筆者の経験上、リフォーム営業は初心者でも売り上げを上げやすく、高い収入を得ることができる職業です。
平均年収
「転職サービスdoda」の年収検索で検索をしたところ、
「建築系/不動産 営業」で平均年収が432万でした。(2021.9.19現在)
リフォーム営業のみの統計は出ていませんでしたが、平均すれば、おおよそ同じくらいかと思います。
筆者の実際の年収額
筆者が実際にもらっていた年収額は25歳で650万です。
650万といっても、会社によっては少ない方だと思います。
リフォーム営業の年収額については下記の記事で詳しく書いているので気になる方は読んでみてください↓
休日、勤務時間
一気通貫型の場合
平日は現場の管理があるため、土日祝日の休みが多いです。
しかし、土曜日は現場が動いていることが多く、休日出勤になることもしばしばあります。
勤務時間は、
朝は現場の始まる8時半〜9時出社。
夕方は17時半30分〜18時を定時としている会社が多いです。
分業型の場合
週末、祝日はお客様との商談、打ち合わせに力を入れるために、水、木曜日休み、または、水、日曜休みの会社が多いです。
あまりにお客様ファーストでスケジュールを組んで、休みが無くなっていた…
という話もよく聞くので、スケジュールの際は自分の休みをしっかり確保しておくと良いです。
勤務時間は現場の管理がない分ゆっくりで、
9時〜18時、10時〜19時の会社が多いです。
残業が多い
リフォーム営業は、どの会社でも残業は多いです。
日中は現場管理業務に追われ、事務所に戻ってきてから事務作業をします。
仕事量や時期、会社にもよりますが、20時までの残業は当たり前。長いところだと深夜まで残業があることも。
慣れてきたら日中のスケジュールを見直して、日中に事務作業を組み込むことで残業を減らすことができます。
しかし、ある程度の残業があることは覚悟しておいたほうが良いです。
仕事の将来性〜リフォーム営業以外にも活かせる経験〜
リフォーム営業になると決める前に、リフォーム営業を続けたあとのことも気になりますよね。
同じ会社でがんばるキャリアアッププランと、キャリアチェンジした場合に分けてご紹介します。
キャリアアッププラン
リフォーム営業も他の営業職と同じくように、
一般職(プレイヤー)
↓
管理職(主任や係長、店長など)
↓
上級管理職(課長、部長)
一般職から管理職といったキャリアプランが描けます。
出世すればするほど、会社経営に関する仕事を任されるようになります。
キャリアチェンジできる仕事一覧

リフォーム営業をやってみたけど、自分に全然向いてる気がしないよー!

リフォーム営業で学んだ知識をいかして、キャリアチェンジしてみるのはどうですか?
リフォーム営業はリフォームに関する様々な知識を勉強するので、他の職業にも応用が効きます。
ここでは5つの具体例をあげていきますね。
施工管理
分業型のリフォーム会社であれば、施工管理にキャリアチェンジするのもアリだと思います。
もの作りが好きだったり、物事を順序よく進めることに喜びを感じる人は、施工監理に向いていると思います。
ちなみに筆者は、工事の知識をより深く知りたかったので施工監理に転向しました。
積算
仕事の流れでちらっと出てきましたが、積算というのは見積もり作成を担当する仕事のことです。
積算であれば営業とは違い、残業時間が少ないですし、休日も安定します。
育児であまり時間がない、産休後の女性が社会復帰するポジションとしてもいいと思います。
分業型の会社であれば、考えてみてもいいでしょう。
インテリアコーディネーター
インテリアコーディネーターは、部屋に置く家具やインテリアを総合的に提案する仕事です。
筆者はリフォーム営業の時に、リフォームで学んだ知識を生かして、インテリアコーディネーターの資格をとりました。
お洒落なインテリアが好きな人は一考の価値ありです。
ちなみに、インテリアコーディネーターの資格がなくても就職できる会社はありますよ。
職人
筆者の知り合いにも、リフォーム営業から職人になったひとは複数います。
まさに手に職、技術さえ身につけてしまえば、独立することも可能です。
1人で黙々と作業するのが好き、DIY等、自分で作業をするのが好き、という方は向いています。
建材メーカーの営業
リフォーム営業と同じく営業職です。
リフォーム会社や工務店に、建材や設備機器を卸す仕事です。
建材メーカーの営業だと、現場に関わることはありません。
現場が苦手、という方にもリフォーム営業で培った知識を活かして活躍できる仕事だと思います。
未経験OK!リフォーム営業の仕事がしたいなら
無資格、未経験OK!
リフォーム営業は、無資格、未経験OKな会社が多いです。
最初のハードルは低いので、挑戦しやすい仕事です。
未経験OKの会社でそれなりに経験を積んで、大手リフォーム会社に転職することもできます。
仕事に活かせる資格、スキル
仕事で必須の資格はありませんが、あったら便利、という資格をハードルが低い順にいくつかご紹介しますね。
民間資格、国家資格、合わせてご紹介します。
整理収納アドバイザー
ミニマリストと同じタイミングで注目されはじめた民間資格ですね。
1級、2級、3級とありますが、2、3級は講座を受講するだけで認定書がもらえます。
試験がある1級も、1次試験の合格率が70〜80%、2次試験の合格率は80〜90%とハードルは低め。
知名度のある資格のため、持っていると信用されやすくなります。
講座の内容は実際に役立つ知識が多いので、持っておいて損はない資格です。
カラーコーディネーター
直接リフォームに関わる資格ではありませんが、内装材のカラーコーディネートを提案する際に説得力が増す民間資格です。
特におしゃれに敏感なお客様の場合、内装材や色合いのご相談が多くなります。
そう行った場合に根拠のあるご提案をできると、お客様の心をぐっとつかむことができます。
合格率は上級のアドバンスクラスで50%以上とハードルは低め。
同じような資格で「色彩検定」もあります。
ホームインスペクション(住宅診断士)
昨今注目されている民間資格です。
住宅の性能を診断する資格で、しっかり勉強に取り組めば、ホームインスペクターとして独立も可能。
資格試験の内容は、リフォーム営業の仕事で身についた知識で解ける問題ばかりです。
インテリアコーディネーター
インテリアの適切な配置や、使用する素材など、インテリアに関する幅広い知識を必要とする民間資格です。
合格率は22〜23%と今までの資格と比べるとやや難易度が高め。
しかし、知名度が高く、インテリアコーディネーターの資格を持っている営業を指名してくるお客様がいるほどです。
建築士
建築業で最難関とされる国家資格です。
1級、2級に分かれており、2021年の1級試験の合格率は15.2%
15%といっても、受験資格を得るための条件もありますのでかなりの難易度です。
難易度が高い資格ですが、持っていればそれだけ信頼されます。
製図や建物の構造、法律などに関する幅広い知識を勉強するので、仕事に役立つことは間違いありません。
しかし、リフォームで建築士の資格は必須とされていないので、リフォーム営業で建築士の資格を持っている人は少ないのが現状です。
稼ぎたいひとはリフォーム営業に向いている
リフォーム営業はお客様と直接やり取りをする仕事ですので、当然、人と話すことに抵抗がない方が良いです。
しかし、トークスキルは仕事をする上で磨かれますし、苦手なひともコツをつかめば案外うまく話せるようになります。
リフォーム営業は、未経験、無資格で挑戦できる仕事の中では
・自分の裁量で働ける
・高収入を目指せる
こういったメリットがあるので、自分で考えて仕事がしたい、高収入を目指したい、そんな方はリフォーム営業に向いています。

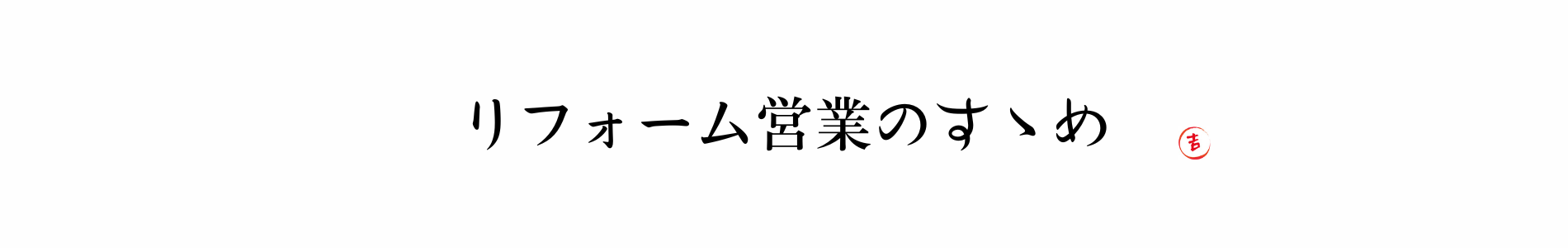
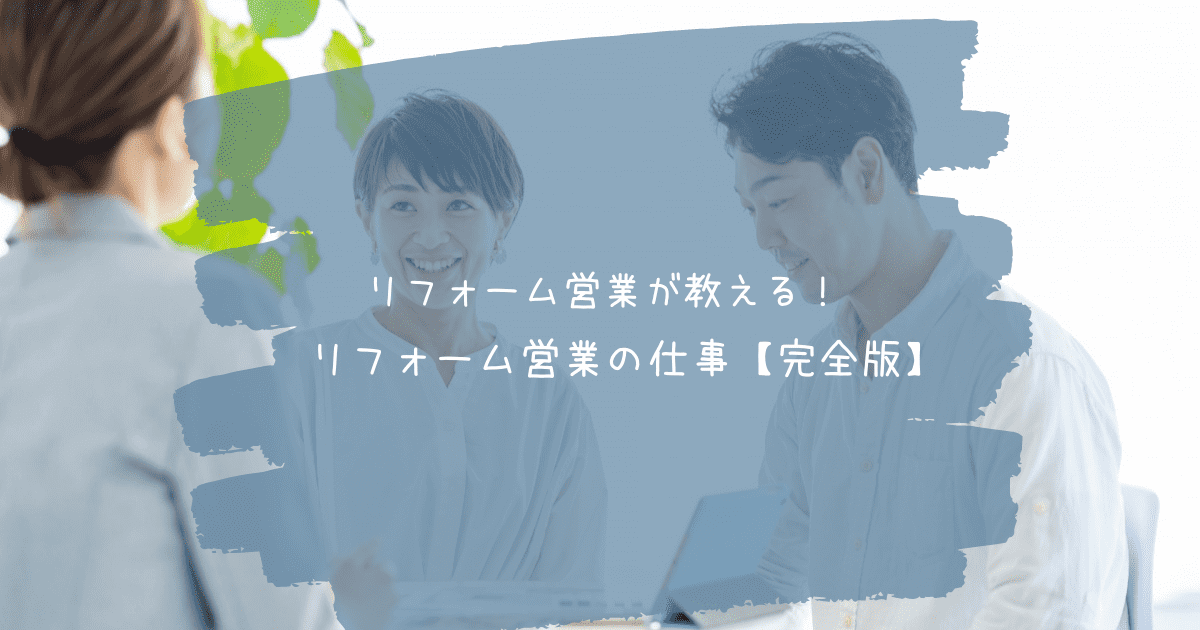



コメント